- ホーム
- 子育てコラム
子育てコラム
こんな親もぅイヤダ!!と子どもに思われないために。
2025/05/23今日は、あえて勇気を出して(笑)過激なスタートにしてみましたよ。
なぜって
無差別刺殺事件の悲しいニュースを耳にすることが、最近多いからなんです。
犯行動機が
東大前駅切りつけ事件では
教育熱心な親の影響で不登校となり、苦しんだ』
千葉の15歳少年による高齢女性刺殺事件では
『少年院に入れば家を出られる』
『(家族に対する)ストレスが限界だった、複雑な家庭環境から逃げ出したかった』
などと述べた。
と報道されているから。
(読売新聞等から抜粋)
こんな親もぅイヤダ!!
っていう思いが募り過ぎて、犯罪を犯す報道を目にするたびに、ひとりの親としてほんとに悲しい思いがこみ上げてきます。
さらに、親子の信頼関係を構築できる親業をお伝えしている身としては、とても残念無念!!!
15歳少年は問題行動が解消されるまで警察と定期的に面談する「継続補導」の対象者だった
と新聞記事で知りました。
(読売新聞から)
子どもの問題行動を認識した時点で、親子の間に信頼関係を築くことができる親業を親が手にしていたら、と残念な思いでいっぱいになっちゃいました。
親業を学んだ方々は
*時間はかかるかもしれないけれど、親子関係が少しずつ少しずつ変わってくる
*メソッドの効果を実感する
*子どもが話しかけてくるようになった
*家庭に笑顔が増えた
とおっしゃっています。
親子関係がギクシャクする前に、親の言葉かけを少しずつ変えていくことを意識してみませんか?
ゴードン博士のコミュニケーション講座~初級編~ではねあなたが笑って子育てが出来るようになる『親業のコトバかけ』の入り口が学べます。
ゴードン博士のコミュニケーション講座~初級編~
親業訓練協会は45周年を迎えました。
今まで、延べ18万人が学んでいるゴードン・メソッドです。
親業を学び始めるのに、お子さんの年齢は関係ありません。
笑ってますか?忙しくて笑顔を忘れそうな時こそ親業の出番です。
2025/05/14『イクメン』という言葉は、2010年の流行語大賞にもランクインしましたが、今ではすっかりその言葉も定着して、言葉の通り、育児をする男性のこと。
子どもの自主性を大切にするために。
2024/11/03浅草橋にある、開智日本橋学園中学・高等学校保護者向け研修会にお招きいただきました。

開智日本橋学園高校では、ボスニアの高校と交換留学制度があるそうです。
ボスニアの高校生たちとの交流会を日本文化の象徴ともいえる屋形船でやりたい!!
日本の高校生がボスニアの高校生のおもてなしにと選んだのが隅田川ぞいの屋形船だったそうです。
屋形船って聞くと、何をイメージされますか?
大人の方は、美味しいお料理をお酒と共に堪能できる『宴会』をイメージされる方が多いのではないでしょうか。
大人の先生方にとっては、そこがネックだったそうです。
でも、高校生たちは自分たちの熱い思いをしっかり先生方に届け、先生方も生徒たちの話にしっかりと耳を傾けて、とても素晴らしいおもてなしの会が開かれたそうです。
「自分で考え、判断し、主体的に行動する」開智日本橋学園の合言葉が、しっかりと高校生たちに根付いているのだなぁと感動しました。
この日は早朝にもかかわらず、150名近くの保護者の皆様がお越しくださいました。

子どもの自尊感情を損なわず、親子の間に信頼関係という心のかけ橋を築くことについてお話をいたしました。
お二人一組になって、子どもの気持ちを体験していたいたところ、こんなご感想をいただきました。
ペアになって実践したのがわかりやすかったです
提案など親が良かれとしがちな行為も良くない行為だったというのが目からウロコ!でした。
日頃チクチク言っている言葉は、子どもの立場になってみると、すごくイライラすることが分かり、言い方を変えるだけで距離も近づくと教えて頂きました。
子どもの立場に立って考える良い機会となりました。
効果的な対応の事例もたくさんご紹介しました。
子どもへの声掛け事例がすぐに使えそうで、実践的で良かった。
子どもが親に話をしてくれる事例を基に、子どもとのコミュニケーションの方法の説明がわかりやすかったです。
子どもに寄り添うことの大切さを改めて感じました。
子どもは、親が自分のことをわかろうとしていることを実感できると、安心して自分の考えや思いを親に話すことはできるようになります。
心のかけ橋が築かれたなかで、子どもの自主性が育むまれていきます。子どもの態度が変わったのは、コトバかけを変えることでした。
2024/05/20あなたは、お子さんの話をちゃんと聞いてますか?
はい、聞いています。
ほとんどの親がそう答えるでしょう。
でも
親はあなたの話を聞いてくれる?
子どもの半分以下しか「はい」と答えないんですって。
あなたは一生懸命に子どもの話を聞いているのに、子どは聞いてもらったという実感が無いって、とても悲しくなっちゃいませんか?
そういえば…。
私の子育て中は、一生懸命に子どもの話を聞いているつもりでした。
つもり…というのはね
子どものことが知りたくて、あれこれ根掘り葉掘り質問したりしてたっけ。
子どものことが心配で、不安で、私の意見を頭ごなしに押しつけてたっけ。
子どもたちが無口になっていくのは、お年頃だから仕方ないって思っていたけれど、親業を学んで分かったことがあったんです。
それはね
話の聞き方には二種類あって
*親が聞きたいことを聞く話の聞き方
↑これ、わたし。
*子どもが話したいことを、安心して最後まで話せる聞き方
↑子どもが、話を聞いてもらったと実感できる聞き方です。
毎日の子育ての中では、「イヤだ!じゃないでしょ!!」なんて、子どもにイライラすることってたくさんありますよね。
そんなときには、親のコトバかけを変えてみませんか?
子どもは『イヤだ!』と思っていることの中身を、安心して最後まで話せると、態度が変わっちゃうんです。
お風呂洗いたくない!って言っていたのに。
2024/05/20子どもは『イヤだ!』と思っていることの中身を、安心して最後まで話せると、態度が変わっちゃうんです。
とお話しした記事の続きです。
私はあなたを受け入れていますよ、ということが子どもに伝わる聞き方で接すると、子どもは心を開きます。
大切なことは、親は何も言わないこと、自分が話すことで子どもの話の邪魔をしないことです。
そしてできるのであれば、そばに行き、子どもの顔をしっかり見ることで、子どもは、自分は親に受け入れてもらっていると、実感できます。
私の講演を聞いた方から、嬉しいご報告をいただいてますのでご紹介します。
A子さんは共働きなので、お風呂掃除は小学生のBちゃんの仕事です。
あれ?いつもと違うなぁ……不機嫌だ…サインかな?…そうだ、こういう時は黙って聞くって言ってた、と思い出して
「イライラしてる?」と、心の扉を開く言葉をかけたら…。
「今日学校で男子がね!!!」
と、せきを切ったようにイライラしたこと、悔しかったことなどを話し始めたそうです。
いつもだったら、そんなこと言ったってしょうがないじゃない…もぅお母さん忙しいだから、早くお風呂を洗ってきてよ!って口を挟んでしまうところに待ったをかけて、言いたいことをごっくん飲み込みながら、うなずきながら、あいづちの言葉をかけながら、頑張ってBちゃんの話を最後まで聞きました。
するとBちゃんの態度が変わり
「あぁースッキリした、お風呂洗ってくるね」って笑顔で、言ってくれたんだそうです。
このように、あいづちの動作やコトバは、私はあなたの話をちゃんと話を聞いてますよ、という親の姿勢が伝わり、子どもは、自分は親に受け入れてもらっていると、実感することができるのです。
親からあれこれ意見を言われないことで、子どもは自分の話を、さえぎられずに済み、自分の考え、気持ちが親から否定されないので、話したいことを話せます。
子どもは話を聞いてもらえる安心感を持ちながら、親に黙って聞いてもらううちに、胸の内を吐き出しながら、いいことも悪いことも、ありのままの自分を見つめながら、自分自身と向き合うことができるようになります。
-
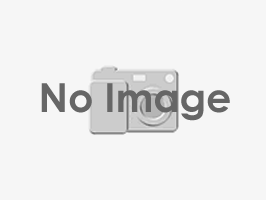 子どもは聞いて欲しいんです。
かえったらなにからはなそうきょうのこと 文部科学省で長年行われている楽しい子育て全国キャンペーン「家庭で話そ
子どもは聞いて欲しいんです。
かえったらなにからはなそうきょうのこと 文部科学省で長年行われている楽しい子育て全国キャンペーン「家庭で話そ
-
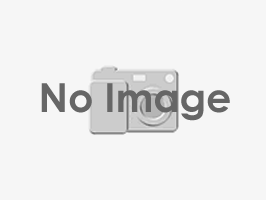 うちの子は反抗期が無いんです。
「うちの子は反抗期が無いんです。大丈夫でしょうか」TVの思春期の親の街頭インタビューなどで、たまに聞かれるフレ
うちの子は反抗期が無いんです。
「うちの子は反抗期が無いんです。大丈夫でしょうか」TVの思春期の親の街頭インタビューなどで、たまに聞かれるフレ
-
 信頼関係が深まるかどうかは聞き方次第だったんです。
こんな聞き方があったなんて知らなかった!親がコトバのかけ方、子どもの話の聞き方を意識することで、親が根ほり葉ほ
信頼関係が深まるかどうかは聞き方次第だったんです。
こんな聞き方があったなんて知らなかった!親がコトバのかけ方、子どもの話の聞き方を意識することで、親が根ほり葉ほ
-
 子どもの態度が変わったのは、コトバかけを変えることでした。
あなたは、お子さんの話をちゃんと聞いてますか?はい、聞いています。ほとんどの親がそう答えるでしょう。でも親はあ
子どもの態度が変わったのは、コトバかけを変えることでした。
あなたは、お子さんの話をちゃんと聞いてますか?はい、聞いています。ほとんどの親がそう答えるでしょう。でも親はあ
-
 お風呂洗いたくない!って言っていたのに。
子どもは『イヤだ!』と思っていることの中身を、安心して最後まで話せると、態度が変わっちゃうんです。とお話しした
お風呂洗いたくない!って言っていたのに。
子どもは『イヤだ!』と思っていることの中身を、安心して最後まで話せると、態度が変わっちゃうんです。とお話しした